木製ケース エフェクター の巻 ( 其の二 )
ギター のエフェクター をシンセ に使っていたが、入力レベルが違うのでセッティングが面倒になり、シンセ 用に
新しく作る事にする。どうせ作るなら目一杯 音を変化させたいので エフェクトモジュール 6個分とする。
シンセ はステレオ出力なので、レベル入力調整用に ミニブースター を個々にかませる。デジタルシンセ の中でも
かなり硬く キンキン する音を、どうにか柔らかく こもった音にしたいので トーン調整 も強く効かせたい。
オーバードライブ 2個、コンプレッサー 2個、フェーザー 1個、クライベイビー 1個、入力調整用に ミニブースター 2個、と
決めて、ひとつづつ製作していたら クライベイビー で引っかかった。回路自体は シンプル だが作動しない。何で?
憂鬱なコイル または共振回路
クライベイビー は簡素で部品点数も少なく、それでいて音の変化が劇的で面白く、赤ん坊の泣き声 または猫の夜鳴きの
ような変な音。簡単に製作できるので私にぴったり、などと思ったのが大間違い。チョークコイル の使用は初めてだが、
ただ単に エナメル線 を巻きつけて あるだけにしか観えない。ところが実際は非常に奥の深い厄介な ブツ と判明。
コイル を使った共振回路は、調べてみると回路の基本との記述があるが概念が判りにくい。ネットに載っていた回路図を
見直してみると、抵抗値 470Ω のところを 470kΩ で製作していた事が判明。プリンター が無いので手書きで
書き写していた為だが、慣れてきた頃が いちばん間違えるという典型。プリントアウト するほうが間違えないが、
書き写したほうが回路の全体像が把握しやすいし、プリンターが有ると大きくて邪魔。
( 手乗りプリンター なら安く買います )
それにしても、クライベイビー に使用できる チョークコイル、小型トランス が少ない。販売店も限られていて
選択枠が狭い。まるで ゲルマニウムトランジスタ のようだが、ゲルマ は自作できない。コイル は エナメル線 を
巻いてあるだけなので自作できそうだが、これが大間違い。特殊な金属でできた コア に髪の毛よりも細い エナメル線 を
適度な力で均一に バランスよく巻いていかなければならないし、金属コア も販売されていない。エレキギター の
ピックアップ も繊細で ノウハウ の塊のような コイル だそうな。部屋に転がっている ギターアンプ から剥ぎ取った
大きな トランス が使えないかと考えた。チョークコイル も ピックアップ も トランス も構造は似たような モノ では
ないのか。( え?)
コイル 特性
エナメル線などの線材を螺旋状に巻くと、変化する電流を平坦にしようとする電源の平滑回路に使われたり、
二つの巻き線を近づけると、片方の電力をもう 一方の巻き線に伝える事ができる相互誘導作用。コイル に電流が
流れると鉄や ニッケル を吸い付ける電磁石の性質、コイル に コンデンサー を組み合わせただけで、特定の周波数の
交流電流が流れなくなったり、流れやすくなる 共振作用 などがあるそうな。コア に線材を巻いたり、空芯コイル を
手巻きしただけで電流に作用する原理を発見した事は凄いと思うが、豆粒ほどのものから 近づいただけで
鼻血を噴きそうな 何メートル もの 巨大な ドーナツ型コイル など、多種多様の巻き線が有って楽しいが、エフェクター に
使えそうなものは少なく、電源用の トランス を応用しても、他の電子部品が吹き飛びそうだし、勿論 共振コイル としても
作用しなかった。自作スピーカー の ネットワーク を製作する為、音質の良いと云われている お高い 空芯コイル など
買わず、特性の良くなるように太めの ” 安い ” エナメル線 を購入して、ダンボール で フランジ を作り、手巻き製作
したが、均一に巻くだけなのに、治具 が無いと トン でもなく面倒で厄介な作業だった。最初から、kg いくらで売っている
しっかりとした フランジ に巻いてある 巻エナメル線 を購入して、そのまま利用すれば楽とも考えたが、適当な モノ が
販売されていない。それならばと、スピーカーユニット に使われている コイル を剥がして利用しようと、雑多な自室を
物色しても、そんなもの無い。なんだかんだと ネットワーク は作れたが、上手くいかずに頓挫しそうになったものです。
この巻線部品、ビデオデッキ の ヘッド にも使われているが、初期の頃は部品ひとつ 一つを手巻きして、手間を掛け
繊細な女性の手で丹念に作られていたそうな。その後、ビデオヘッド の 自動巻線機 が開発されて ビデオデッキ の
価格は安くなったが、極細の線材を均一に均等に断線せず、コイル特性 も揃えて製作できる 自動巻き線機 の開発は、
悪戦苦闘の連続だった。その為、量産品でない 特殊な コイル は、未だに人の手で巻き上げているのだそうな。
つづく。

出来上がらない エフェクター
木製ケース 真空管 エフェクター の巻 ( TubeWay Effector )
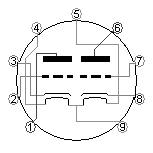 トランジスタ の エフェクター も良いけど 真空管 も好いのか、過剰入力を加えると 石 の チップ
トランジスタ の エフェクター も良いけど 真空管 も好いのか、過剰入力を加えると 石 の チップ
は ガリリンッ と硬く歪む、オーバーヘッド が狭い、低いのか、ギターアンプ は チューブ を有難く
使ってるのを考えれば、しかし 1本 数千円 もの ガラス の 増幅器 など、Tubeこべ言わず
ロシア製 SOVTEK の 12AX7WB を安く購入。パッケージ の アルファベット が引っくり返った
ような ロシア語 が好印象。TUBE エフェクター を作っておられる 松美庵さんのページ の 回路図
から簡単そうなものを選び製作。ヒーター も灯らなければ ハムノイズ も聴こえない。12AX7 が壊れたか、オペアンプ の
接触不良か、DC9V だと電圧不足か AC か、回路図 眺めても間違っては、9ピン の配列は 右回り、じゃない。 右 から
1番だった。無理矢理 配線を引き廻し、ユニバーサル基板 が グッチャグチャ。 シベリア鉄道 よりか道のりは遠いのか。
凍てつく大平原の雪解けの、足元覚束ぬ 真空ヘッド、恐々9V の ワニ口クリップ を繋げれば、オレンジ色 の ヒーターが
温かく点ると思ったら、蛍の光よか頼り無し、電圧低いか接触不良。 暫く、 今しばらく御待ちを、 暖機が必要、
1分も掛からぬ内、オーバードライブ が起動、モコモコ低音 だけの高音不足かと想たら、耳が痛くなるほどの高音も、
力任せの ハムバッキングコイル弾きも受け止めるほどの性能。こりゃ安い買い物、ロシア の チューブ。
真空管素子 の代替品が トランジスタ と思えば、NPN トランジスタ が二つ 真空封印 されてるのが TUBE だと (エッ?)
考えれば、チューブ 1本、コンデンサー、コイル、炭素抵抗器 を 基板 へ乗せれば 太い声 の Tube CryBaby を
作れないかと トランジスタ を 真空 へ置き換え、アレコレ定数を変えて ギター を弾けば、ジャリジョリ 煩いだけ。
松美庵さんの Valve Caster へ作り変えると Tube の本領発揮。指先のほんの少しの動きにも反応、篭った音も
太い音も柔らかい高音域も、ピックアップ の切り替えだけでも、ギター の ボリュームノブ を少し捻っただけでも音が
自由自在。 9V電圧 の オペアンプ や トランジスタ回路 は、石 の内部歪み、発振が厄介、設計が難しいが、Tube の
飽和状態は、包み食って和音となる利口な増幅器 、楽器の音色 へと変わるのだそうな。
真空管の欠点は消費電力、発熱が多く、1本 の価格が トランジスタ の 十倍以上だが、容量の多い 電解コンデンサー、
発振防止 セラミックコンデンサー も使わず、構成部品、残留ノイズ極少の 増幅回路 を作ることが可能。シールドケース
にも入ってない 素人製作 の 空中配線 TUBE エフェクター が、トランジスタ や オペアンプ満載 のものより ノイズ が
少ないとは、どうゆうこっちゃ。 12AX7 は 12V駆動 だから其の名前、ということは、12V〜16V の 電圧 を与えれば
本来の性能を発揮、倍音が増える、歪みが滑らか艶っ々、サスティーン も伸びるの良いとこ取り、3端子レギュレーター
通さず 16V ACアダプター 直接繋げば、ヒーター が光り輝き 増幅音 が増え、球の発熱 は、熱 っ 。
コンデンサー通過電源 じゃないからなのか、ラジオ の 電波 や リップルノイズ が入る。9V 駆動でも充分良い音だから
と戻せば、ギター の音が聞こえない。壊れたか、ヒーター が焼き切れたか、だけんど 豆粒 は光ってる。ギチギチ
空中配線の接触か、良かった好かた壊れてなくて。 9V 圧へ戻っても 残留ノイズ が聴ける、チューブ の傷みか。
トランジスタ や オペアンプ だと壊れて使用不可のような劣悪環境にも耐えられる、MIL規格 並みの素子じゃないのか、
と、 。 100V 延長 コンセント の ケーブル を 作業台 がわりに使うと 外来ノイズ が入るので止めましょう。
to 、パソコン 通さず Valve Caster を作動させると、おとなしく倍音少ない素音へと変わり、チリチリ音 も聴こえない。
この 負荷ノイズ は何故か PC へ尋ねれば、ライン入力 の クリップノイズ だったのは偏拍子。12AX7 は ゲイン が不足
気味、1本 ぐらいじゃ オーバードライブ用 は役不足、だったら 増幅増加 の 数珠繋ぎ、2列駐車 の ドライブ駆動 は
ピックアップ 切り替え、トレモロアーム を掴む、余った 巻き弦 を指で弾いただけでも音が聴こえる 聴診器 のような
楽器 へ様変わり。 こんな ギター 弾けない。 4558D+12AX7 は ゲイン を絞っても、之でもかと云わずもがなの歪み
っプリ。 シングルコイル の ピックアップ だったら善い、作動電圧 が低過ぎる、電子部品 配置も、DRIVE 可変器 の
リード線、各部の配線 を最小限の長さへ切り詰める、IC の内部歪みだから コンデンサー定数 を変更、回路組みが
間違ってるのか、入力インピーダンス が大き過ぎるのか GAIN が原因か。 ミニブースター は増幅率を変えるのでは
なく、ゲイン調整 が役目、というのが眼にとまり、ハムバッキング → ミニブースター → 4558D+12AX7 ⇒ ミキサー と
繋げれば、太弦 低フレット 弾けば キュォン と、今日から早速 バン・ヘィレン。 と云うよりも、バン・ホーテン の ココア
飲みつつ考える、 か。 コード を カッティング しつつ ビブラート、アルペジオ を挟み ミュート ハーモニックス、トレモロ
アーム を曲げつつ 変拍子 の インプロ を弾く、などと素っ頓狂なことを考えてると何時までも テクニック はつかづ、
運動不足で肩も上がらず。 暫らく使って、久し振り光らせたら 極少信号 を受け付けない。ギター の ボリューム限界
か、ジャック か プラグ か手作り シールド の ハンダ盛り不良 か、トランジスタ が壊れたか 電圧不足 か。 この場合は
接触不良か回路の接続間違いが殆んどだと、ドタバタ 考えても最大限入力以外の音が、間引かれた デジタルノイズ の
様。 アッテネ―ター や トレブルツマミ を チマチマ廻せば、音質、歪率共々、ホン の少ししか変化が無い。
TUBE が壊れたかと想ったら、ソケット と ピン の接触不良、ジャリリりリ の雑音と共に元の音色へと変貌。
こんな ガチガチ の堅い ソケット が接触不良とは。 接触不良は ソケット だけじゃない。 可変抵抗器 を彼是変え、
ハンダ も付けずの リード配線 は、酸化皮膜の集合体。 エフェクター基板 を振って ジョリッ と云へば、雑音聴こえれば、
それはもう、何処かの接触不良か 電子部品 が壊れてる。 今まで 微細信号 の削れた音を聞いてたとは。 とほほとは。
タバコ 1箱分の、3本 の中古 6BN8 を購入、この真空管、12AX7 と ドノ程度の性能、音質、増幅量が違うのか。お安く、
扱い易ければ、耐久性が良ければ、6BN8 へと、などと考えたのが素初心者の浅い能力性能。 9ピン だから、一寸ぐらい
ピン配列 が違っても動くだろう、ヒーター が光る灯る、これだったら、 動かない。 焼けた臭いも スパークノイズ も
聴こえず、無音状態。 12AX7 へと差し替えても作動せず。 新しく 6BN8用 の 回路 を作ればよいものを、
TubeDriver回路 が破損。 知識の無さと イイ加減さの差が、嗚呼、困ったものとへ。
つづく。
Orange Squeezer Comp
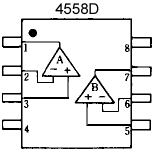 製作中
製作中
MXR DynaComp
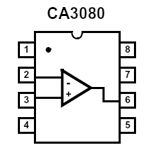 発振中
発振中中古の 国産ベース を格安購入。 この エレクトリックベース、見た目通りの物凄さ。 ボディー のシール を剥し、上塗り
塗装を削り、木目調ギター へと変え、フレット、金属部品を磨き、ポット の接触不良、トラスロッド調整、と思うが 凶、
ボディー磨きの所で、もう手が痛い。 剥離剤使えば良いが、劇薬は使いたくない。 これはもぅ、雑多な部屋の
インテリア、か?。 と商品が来てもない今日、昨日の此の頃。 ---流石は日本の流通、何百キロ 離れてようが
お構いなし、一日の移動とは。 早速中身を拝見、画像通りの物凄いベース、ベース の ベース か?。レスポール型
よか軽い、ネック が長く エレクトリック・ギター が野暮ったく見える、とは言わないが、こりゃ良い買い物。
ネック と ブリッジ、コントロールプレート、エンドピン を外し、金属ヤスリ を使っても、鑢目の中へ皮膜が入って
ボディー の塗料は中々削れない。金属ブラシ を 電動ドリル へと取り付け、グワリガリ 削れば簡単だが、ブラシ も
無いし、削り粉 が部屋を舞って掃除が大変。ヤスリ の淵を使って荒く削り、残った皮膜を 無水アルコール 振りかけ
ふやかし、カッター を ヘラ の様に滑らせれば意外と作業が捗る。元々の ボディー は メタリックレッド だったのか、
銅版画技法の ドライポイント 網目模様の如く、良く言えば バン・ヘイレン の フランケンギター にも見えなくもないが、
弾いてる時、塗装が剥がれるのも厄介だ、荒目の 紙やすり と 液体クレンザー、車用コンパウンド使って フレット、
金属部品 も磨けば、あ〜ら不思議、\6000 の ベース には観えない。 バーゲン品 の新たな ストリングス と
張り替え、さて チューニング、と思つたら、1弦 の ぺグ に手が届かない、流石は ベース、作りが違いまんな。
ギター と御変りなく 音叉 使って 3弦 の 5フレットハーモ と合わせても音程が低い、もっとか?、まだかょ、弦が
キリリッ、バチッ、と千切れる、新品の ストリングス が。 3本 だけ張っても、長いネック が弓の様、撓る。
8フレット 付近の弦高が 10mm もあるのは、トラスロッドのナット が ピクリ とも動かないのは ,
ど〜ゆ〜こっちゃィ。 ベース は 3弦 が A(ラ) 440Hz、だった。 ベースってこんな テンション 緩かったのか。
というよりも、弦の巻きが大雑把。動画の説明、3弦ハーモ は 440Hz の音叉加減、全く耳が鍛えられてないだけだった。
だがちょとまて、ベース は 1オクターブ低いから切らない様注意ってのは?。 もぅ切れても歌よ。ソフト・チューナー使うか。
楽器、機械は奏者、使い手の反映。弓ネック、破断金属線、ボディーの軋み、女性のような繊細 ヘッドネック が折れなくて
良かったですがな。 ネックポケット が ギッチギチ、メイプル の柔らか 光沢ネック。 流石は 日本製、仕上げや見た目に
世界一煩い消費者の満足度。 それでも海外製を有り難がるのは 島国 だからか。 さっさと弾けばよいものを、ベース を
弾きたいんじゃなくて 楽器 が好きなだけか?。暫し眺めれば、余りにも ヘッド と ネック との流れが細すぎる。 これだと
コンクリート の壁へ軽く接触させただけでも傷みそう。 でかく ゴツく、Jagdtiger重戦車 のようなのが BassGuitar だと
思ってたのが大違い。 見れば観るほど、3ピース か 1枚板 だか判らないほどの、磨けば研くほど、緻密な作りのこの
ベース楽器、制作工程や技術力の事を考えれば、サーバー の設定など微々たるもの。 WW II のドイツ軍戦車は
重圧長大の失敗作だったそうな。 しかし、戦闘員の疲労を最小限に抑える サスペンション構造、白く塗られた内部隔壁、
エンジン の熱や騒音が伝わり難い構造設計、硝煙排出用ベンチレーテッドファン、自動消火器、ヘッドフォン と 喉の
マイクロフォン、外見は 彫刻刀 で削ったような荒く、均一な溶接跡。 大雑把な作りの印象が、トンでもなく考えられた
構造体 だったとは想わなんだ。 ここんとこは、もうちょっと削ったほうが良いよ、ココ もね。 それと 力 入れ過ぎだよ。
「 誰だ、あの オヤジ はよッ!、なんの権利があって俺にそんなこと言うんだよッ」 と新人の若い ビルダー。
「彼のことを君は知らないのか?。あの方は ミスターフェンダーだよ。作業現場を見てまわってるのさ、君に ノウハウ を
教えたんだよ。」
説明受けた血の気の多い 新人君、顔が真っ赤の真っ青、意気消沈。 流石は クラフトマン、年季が違いまんな。
幾ら トラスロッド を締めても、技術力の無さか、少量の潤滑剤を塗ろうが ネック は弓道の如く反応無し。大体が、弦を
張らずもがなの順反りは、トラスロッドの力 が弱ければ 60kg〜80kg の弦力に引き寄せられる。ナット の締め込みの
加減を間違えると ロッド が折れたり、捩じ切れたり、指板 が割れ剥がれたりと、素人には修理不可能なのだそうな。
ワッシャー を噛ませば ロッド が締め込めるのか?。 六角鉄ナット の角を ヤスリ で削り、プライヤー固定。電動ドリル
使って ネジ の部分を削り取り スペーサーを、これを入れると 二度と外せない、ロッド の ネジ部 への引っ掛かりが無い
のを確認、トラスロッド の ナット を締め込む、ギギッ、キリリリリッ、嫌な音、ロッド が折れるか 螺旋 が潰れるか、
ロッドナット が壊れるか、フィンガーボード が割れるかどうなんか。 弦を チューニング、 少ししか変わらない、
マシンヘッド のほうが反り返ってる雰囲気。 ネック の取り付け角を変えなきゃ駄目か?。
黒人スラップベーシスト は指が入るほどの弦高奏法、お構いなし。
そんな事云われても弾けない。
十字溝 の トラスナット が壊れそう。 安い 6穴ナット を買えばもっと締めこめるか折れるか。 まァイイか。 ピックアップ
を取り付け暫らく弾いて、エレクトリックギター へ持ち替えると、低音の全く無い ぺッケペケ の安い ウクレレ の様、とは
云い過ぎか。 ストラトギター の 6穴ナット だったら、もっと 力 を込められるかもと ベース の ナット と入れ替え、グリス を
チョイ とつけ、締め込む 々。 入るは入るわ、手の平 トンネル・ボーリング・マシン の様。 ところがそんな簡単じゃない。
ナット を締めても 余り変化 がない、どころか突然 竹 のように ネック が バックリ 真っ二つ、何時まで締めてんだよ、この
スットコドッコィ、限界値だ ってのが、まだ判らねえのんか?。 と ツインネック・ベースギター へと変わらぬうちの、
フレット 磨きかな。 ハンマー打って浮き上がりを確認、鉄紙ヤスリ 使って フレット の高さを調整、液体クレンザー磨き、
植物性オイル を塗れば、ローズウッド指板 が サラサラシットリ、錆び易い ストリングス も スライド奏法 ツッルツル。
ブリッジコマ の高さを変え、無料の メトロノームソフト を ダウンロード。 メトロ の クリック音 が消えれば リズム は完璧
なのだそうな。 JazzBass は ジャズ だけの演奏楽器ではなく、Precision は プレッション でもない。 ベースギター は
ピック を使わない、指弾きが正統であることもない。 ソフトウェア・チューナー を通せば、ベースって こんな テンション
強かったのか。 指が痛い、ピック使えば弾く位置、角度、強さが ホンのちょっと違っただけでも音量、音色、響きが大きく
変わる。フロントピックアップ と リア の出力、トレブル 回せば、これでもかと 音 が変化。 殆んどの フレット、それ以外
でも ハーモニクス が響くわ鳴るわ、ベース・ギター は エレクトリック・ギター よか 楽器の表現力 が狭いとは、誰が云うた
のか。 ピック弾きでも、スライド させただけでも 指先 が、弾いてられない、全身汗だく。 メタリック・レッド の ボディーへ
流れ乾いて トラ目模様。 それは余計な 力 の入れ過ぎ、上手い演奏者ほど、殆んど リキ を入れない、強く弾いても、太く
長い ストリングス を濁らせない、深い ビブラート も軽やかである。 などと云われても、握力測定の様。
腕を磨くより、ベースギター の見栄えを変えたほうが良楽いのか、ヘッド の メタリック・レッド を削り剥がし研けば、中々
の木目模様。 しかし、バタースコッチ色 の ネック との相性が、マーガリン を塗るわけにもいかず、水性の 黄色塗料 を
薄く溶き、ホン の少しだけ塗れば真ッ黄色。 乾けば色も薄く、 ならずのそのまんま。 薄い皮膜を剥し、他の色を混ぜ
バター色 を調合散布。木目が全く見えない。 塗っては剥し、ヌッテは剥がしの繰り返し。 メイプル色 の 水性二ス 買わな
くっちゃ駄目か?。 水性二ス は、ちと高い。1ガロン だ、お買い得の 3リットル、送料無料と云われても、200円 30ml の
透明水性 を買い塗れば、こりゃ塗り易い、接着剤も表面処理も塗料 も昔とは大違い。色を少し混ぜ 3回ほど塗り込めば
木目ヘッドのスコッチ色 とはいかないが、ボディー への塗りしろが、無駄無く塗れば RED が栄える映える。細かい傷の光
拡散も、塗膜が入れば正反射。 之くらいだろと ネックの角度 を変えれば音が変わる、弦高を キッチリ 合わせても音色が
違う。 葉書きの厚さ、 0.1度ぐらいか?。 という事は湿気や気温の影響音質変化量が エレクトリック・ギター よか多い、
ストリングス の振動幅、質量も大きいからか ?。などと考えること 少3秒。
赤い ボディー を磨けば メタリック の粒子が良く判り、繋ぎ目も良〜く、 3ピース だったのか。 6ピース かも、アッシュ か
バスウッド か、などと考えるのは無駄なのか。 エレクトリック・ギター の ポールピース を、そんな チマチマ 高さを変えて
も余り意味無いですよ。要は弾き方、楽器への接し方です。そんな暇があったら リズム の練習です。 の アドバイス の
ほうが有意義か?。 今まで ボールピース かと思てたら ” ポールピース ” だったとはなんてのは、どっちでも良いの
か?、ポールピース は言い難い、というのもかな。 筆ムラ の平坦度を増そうと 無水エタノール を 水性二ス へ付けた
途端、皮膜が溶けて斑模様。 水彩画材用の保護膜 だからか乾けば 水 には融けずも植物性溶剤には良く馴染む。
其処だけ塗り込み乾いたら 紙ヤスリ と コンパウンド磨き。 何時まで経っても終らない。 手が痛い。 どころじゃない。
ボディー材への食い付きが弱く、プラスティック へ 木工用ボンド を塗ったよう ペリペリ 剥がれる剥れる。 餅屋はもちや。
とほほっ。 などと考えてる場合ではない。模型の色艶が本物と違う、本当の迷彩色はなどなど、先へは進まづ、
駁模様の表面へ塗っても意味が無い。剥れるわはがれる、透明クリアを塗り乾かし、指紋がつかない程度まで、
此処で磨いて生乾きだったら困る、ベースの練習を乾燥時間へ充てれば 一石二鳥、ブリッジ、エンドピン、
ストリングガイド、ペグ、ネック を取り付け、弦を チューニング、 バキョッ、鈍い音、ロッド が折れたか?。 丸い弦の
ガイド が ネックの台材 ごと吹き飛び円く陥没穴、ネック材ってこんな柔らかいのか。 硬く重く作れば音は良い、しかし
ネック落ちなどの演奏上の支障が。 生乾きの木材へ ネジ を挿し廻し、引っ張りの力を加えるのは御法度だよ、
そんなことも知らないのか、ベース なんざ 80年早いわ、6弦ギター弾いてろよ、このすっとこどっこい、 か?。
ガイド の位置を変えると音が変わる。割り箸を丸く削り、木工用ボンド を塗って圧入。暫し乾かし弦を張ると 3日後、
ストリング・ガイド が無い。木ネジ を締めた時の感触が緩いと固定されてない、これで外れないと思ってるのは 己 だけ。
大きめの ドリル を使って破損箇所の穴を広げ、木片を円柱削り、ボンド を塗り優しく叩き込む。出っ張り部分を
カッター で削り取り、ガイド を取り付ける。木螺子は廻りが止まった時が最適圧、それ以上締めると 木材のネジ切り が
壊れる。 コントロール・プレート を開けば、ジャック の アース錆び、半田盛りの リード配線 を変えれば、ノイズの低減や
出力の増量が可能かも。 スタンダード の 回路図 を観とけばよいものを、適当繋げれば, アルミホイル の シールド を
貼り、ノイズ が激減。 弦の振動を良く取り込む様聴こえ。 フロント、リア の、どちらかが ボリュームゼロ だと雑音が零
だけんども、弦音 も聞こえない。 これが標準の Jazzベース か?。 やたらと使い難いからと ポット の アース 流れを
切れば音が違う。 だったら トグル・スイッチ を付ければ善いのか。 なんだか方向性が、極性が違うような気が、
なんだこりゃ。 トグル を付け、 スペース が狭く、トレブル と フォンジャック の隙間へ取り付けると
トレブル・ポット が入らない。 小型の ポット へ変え、Tube の音を聴けば、トレブル が トラブ、
音色が変わらない。 大体がですよ、ボリュームポット の接続が標準の
Jazzサーキット図面 と違うのは良いのか。 基本は スタンダード、 だから引き回しを変える。ボリューム は逆とは
ならず、トレブルは、ノブ を絞れば高音成分増量、 あたたた、 そんなの当たり前、それよか トレブルポット の
ノイズ が酷い。 ポット を洗浄、も変わらず、 高音成分は削られず、 このような場合は コンデンサー へ
信号が流れてないか容量不足。 ポット を新品へ変更、コンデンサー の容積増量。 残留ノイズ の
聴こえる最初の JazzBass のほうが良かっ。 プッ。 ものはことあれ、ハードウェア が良くっとも、
弦を押さえて弾くほうが、 こりゃもう練習のみ。 ピック弾きは安定、1っ本 から 5本 は トンでもなく不安定。
という事は、指のほうが ピックアップ を切り替えずとも音色を変えられるということか。 4本の弦、指を滑らせば滑らか、
少しの指先弾きは高音が不得手、安そうな ベース音。 強く優しく柔らかい猫手弾きが最良か?。
トレブル・ポット は ガリノイズ、分解清掃、炭素皮膜、接点を磨いても作動不良。 ナット の締め過ぎか ?。
新品の 100円ポット を装着。 手持ちの余り物 コンデンサー を使ったら容量不足、サッパリ 音色変化無し。
此処は一丁、1個 しか在庫のない コンデンサー を接続。之だったら良い、 好かなかったのは ベース の 1弦だけを
弾いて押さえを放し左手 ミュート、 しかしも弦振動が全体を伝わり、弾いてない弦までもが振動、これは善いのか。
ギター は リズム が重くなるから手を絶対 ブリッジ へ置いてはならない。 だから右手 ミュート が苦手ですがな。
なんてのは通らない。 8弦ベース だろうが 12弦ギター だろが、左右の手、ミュート が上手い、最も難しいのは
ミュート である。 なんぞと云われても、リズム の要は消音、 そんな事、判ってても無理、 なんてと考えたらムリである。
つづく。